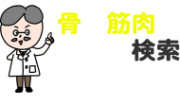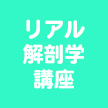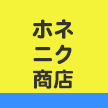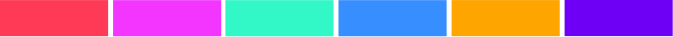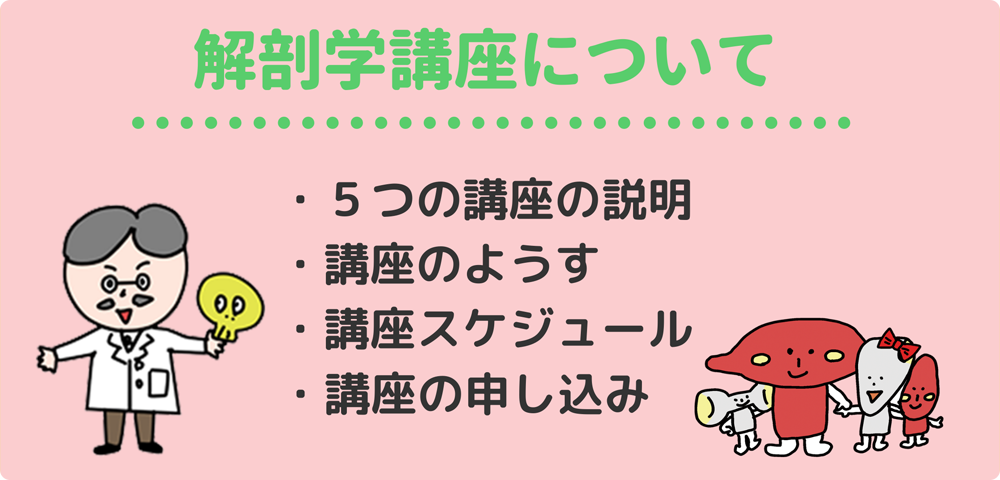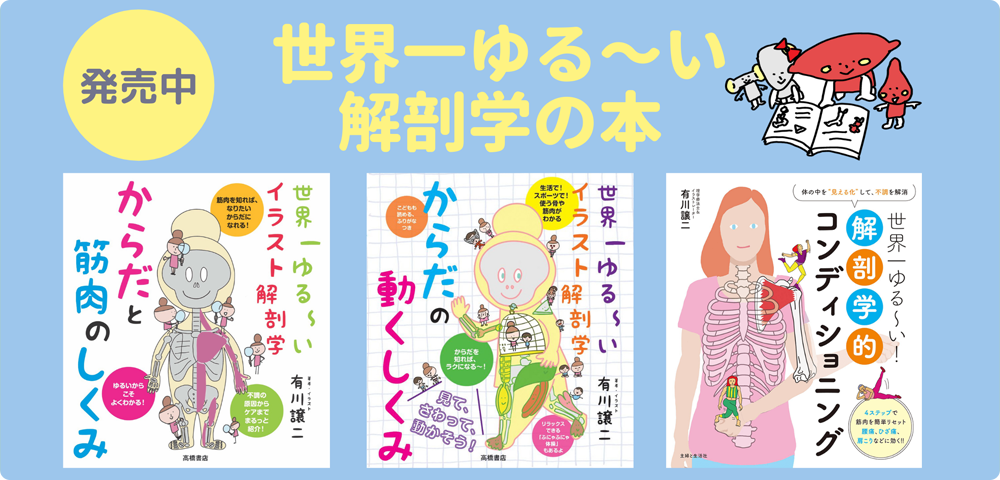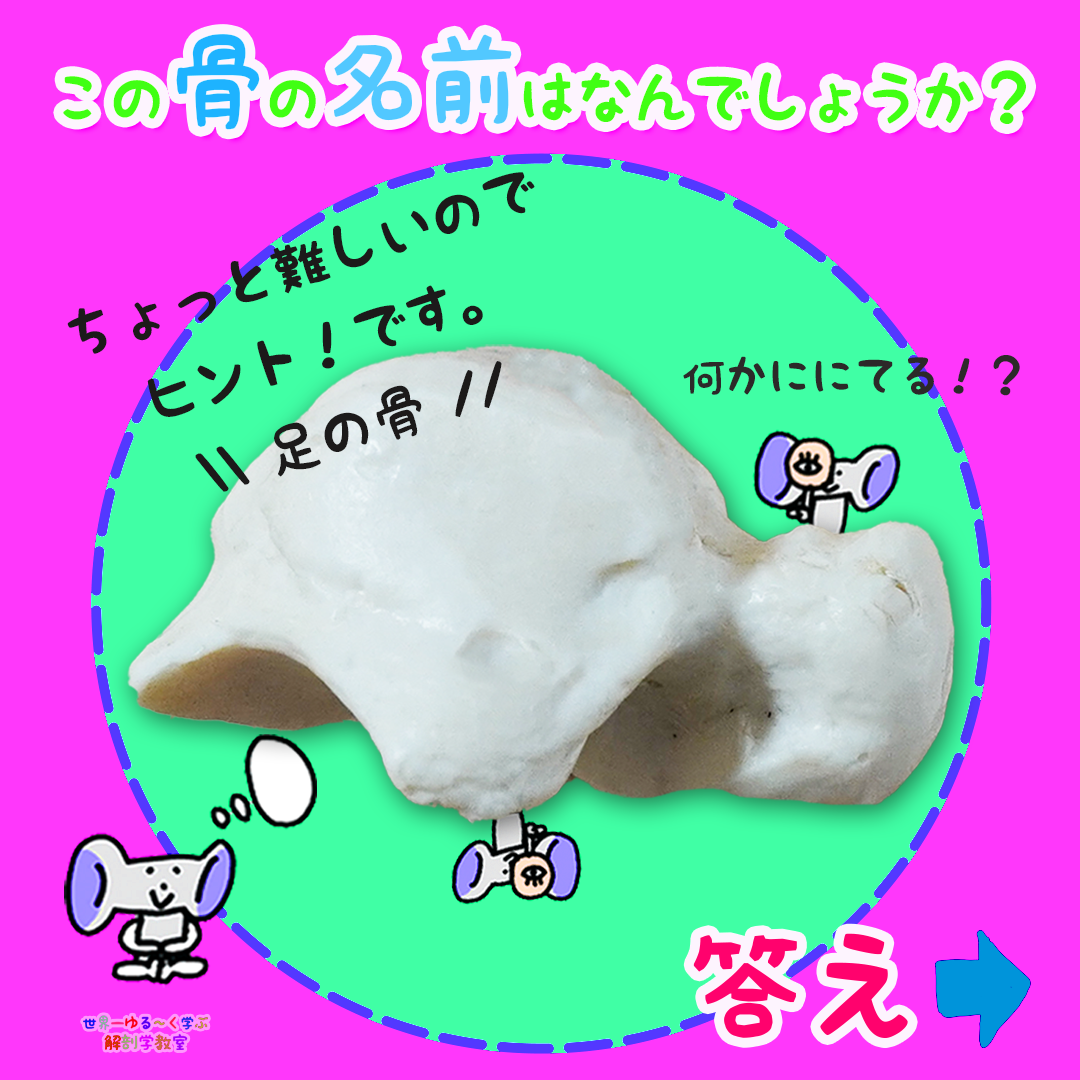今回は、腓骨筋(ひこつきん)のまとめです。
腓骨筋は膝から下の外側についている筋肉です。
腓骨筋を細かくみると、
・長腓骨筋(ちょうひこつきん)
・短腓骨筋(たんひこつきん)
・第三腓骨筋(だいさんひこつきん)
の3つの筋肉があります。
今回はこれらの筋肉をまとめて腓骨筋としてみていきます。
3つあるので少し難しく感じるかもしれませんが、まずはイラストで3つの筋肉がどこついているのかを大まかにみてみましょう。
1.腓骨筋(ひこつきん)を横からみてみよう!
腓骨筋がついている骨の部位は、
起始:腓骨の外側
停止:足裏(親指側)と小指外側
です。
イラストで腓骨筋のかたち、ついている部位、またいでいる関節を確認しましょう。
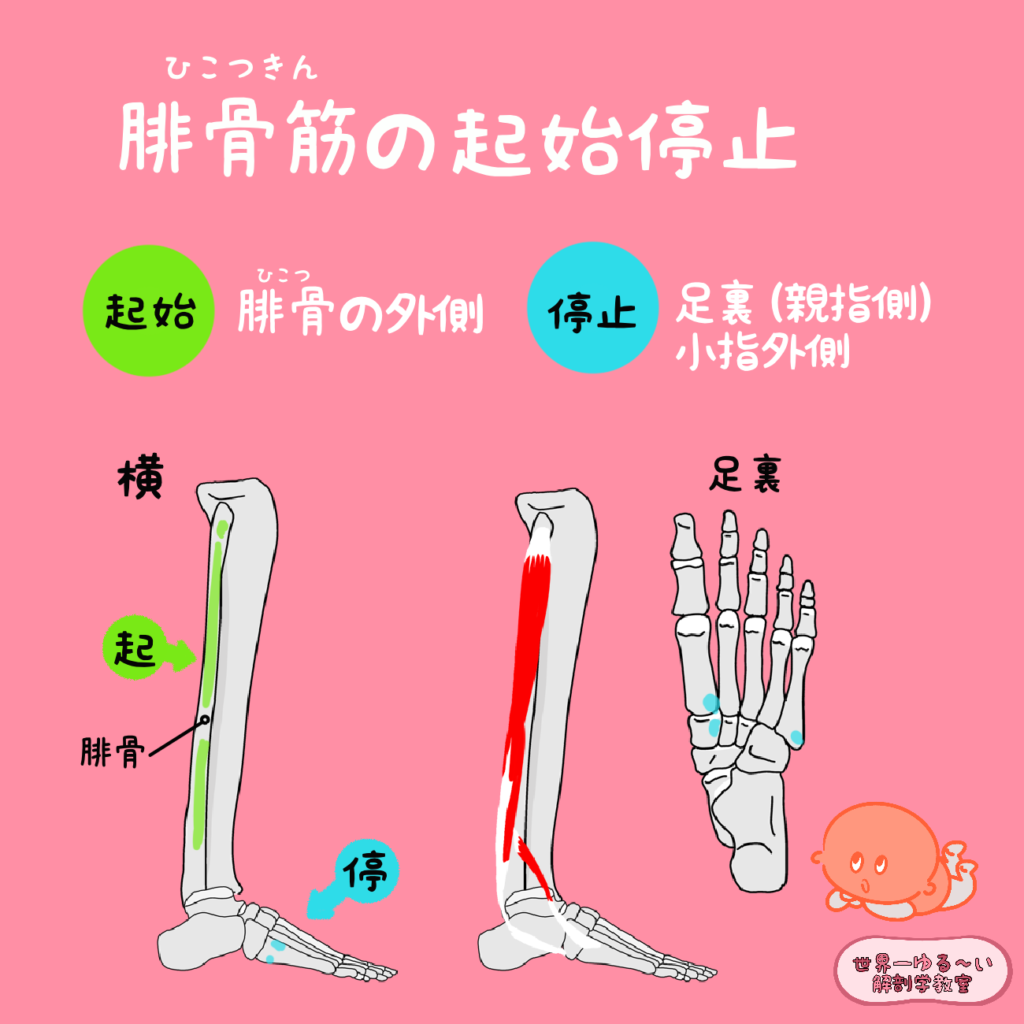
そして、腓骨筋が縮むとどういう作用になるかを考えてみましょう。
腓骨筋の作用を2回に分けてみていきます。
2.腓骨筋の作用 その1
腓骨筋の1つ目の作用は、【足首を伸ばす】です。
外くるぶしの後ろ側を通る筋肉(長腓骨筋 ちょうひこつきん、短腓骨筋 たんひこつきん)が縮むと、土踏まずを小指側に向けるように足首を伸ばす動きになります。
イラストをみて、動きを確認しましょう。

次は、もう1つの腓骨筋の作用をみてみましょう。
3.腓骨筋(ひこつきん)の作用 その2
2つ目の作用は、【足首を外へ反らす】です。
腓骨筋は、腓骨から足裏の親指側と小指の外側についているので、足裏を小指側に向けるように反らす動きになります。

次は、腓骨筋がどんな動きで使われているかをみてみましょう。
4.腓骨筋(ひこつきん)はどんな動きで使いますか?
腓骨筋は、足首を伸ばす動きや、足首を小指側に反らす動きで使われています。
イラストのような、片足立ちで足首を安定させるときも使っています。
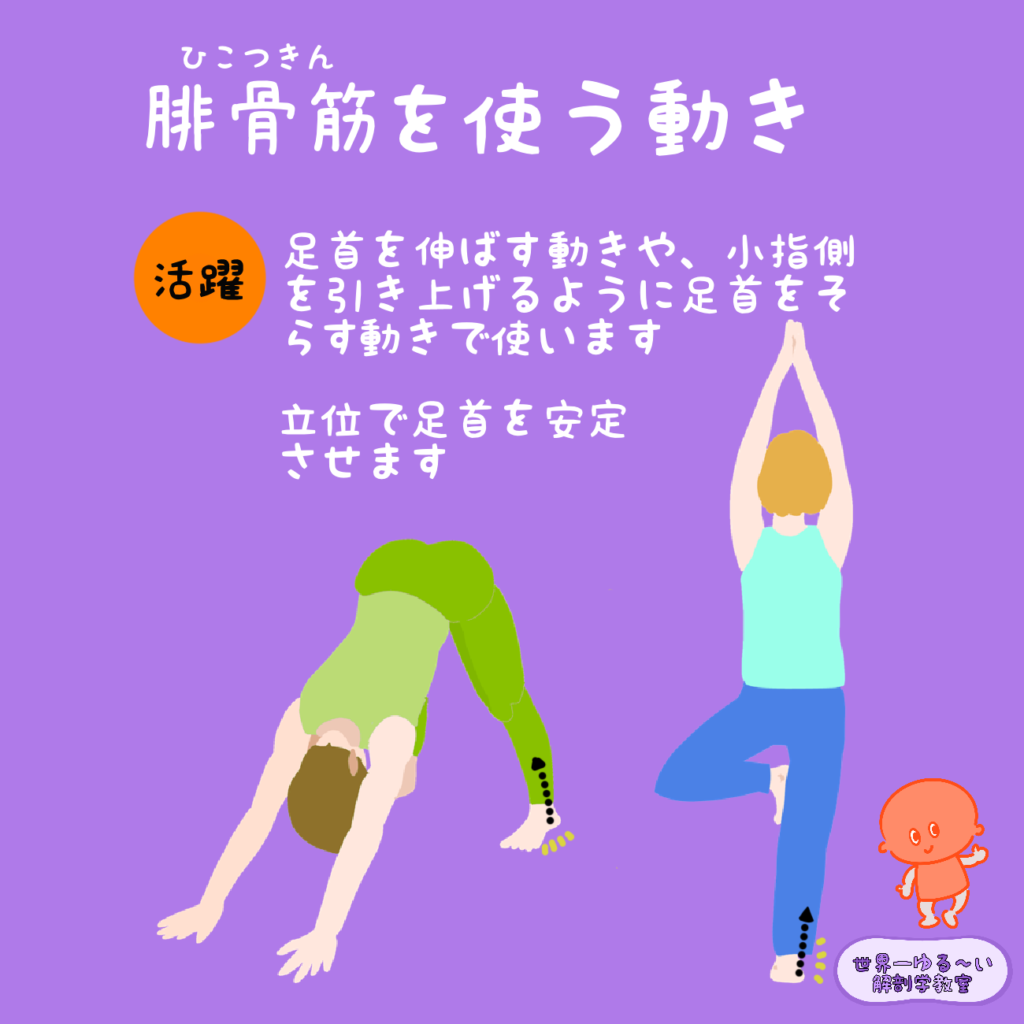
最後に、この筋肉を意識して動いてみましょう。
5.腓骨筋(ひこつきん)を意識して動いてみよう!
そして、いつもとの違いを感じてみましょう。
立位でこの筋肉を意識すると、踵がまっすぐに立ち、足首が安定します。
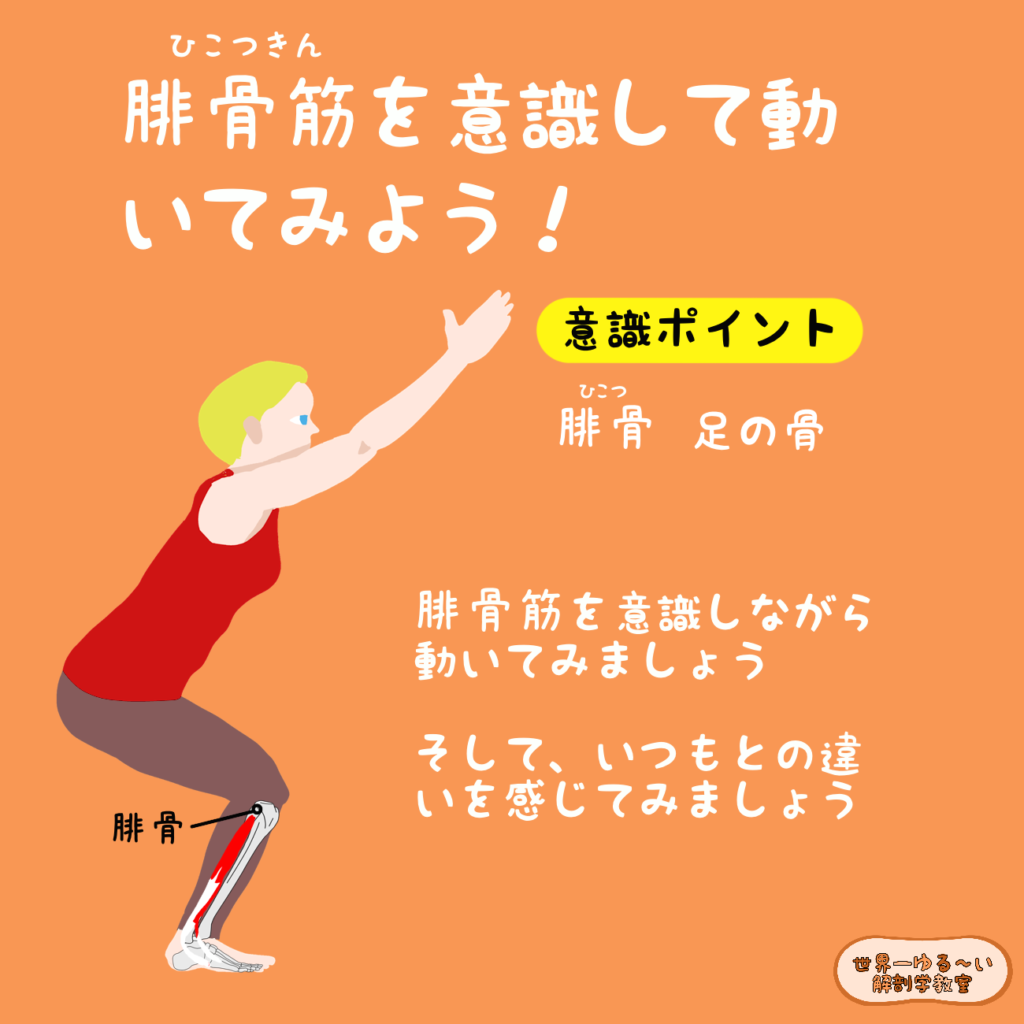
自分の体で、筋肉を感じながら学ぶことで、リアリティを感じる解剖学ボディイメージができてきます。
1つ1つの筋肉をゆっくり学んで、少しずつ解剖学ボディイメージをつくっていきましょう。
ちなみにこの筋肉は、前脛骨筋とともに、足裏のアーチつくりに関係している筋肉です。